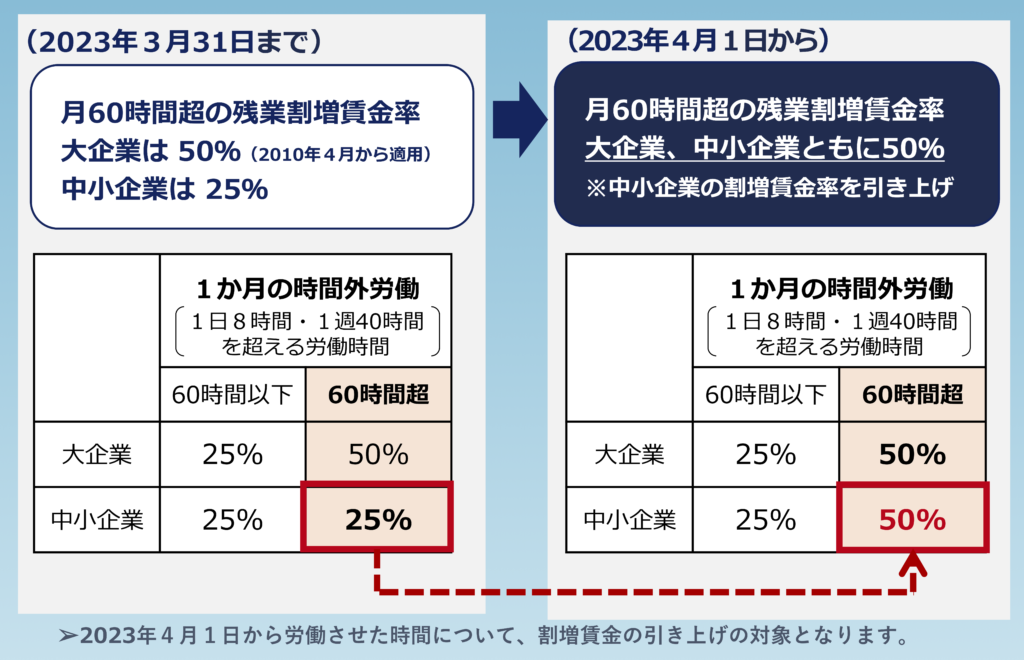令和4年10月3日、第210回臨時国会が召集され、岸田総理は衆参両院本会議で所信表明演説を行いました。演説では「日本経済の再生」を最優先の課題とし、新しい資本主義の旗印の下で、「物価高・円安への対応」、「構造的な賃上げ」、「成長のための投資と改革」の三つを重点分野として取り組んでいくと述べました。企業経営にも関わりが深そうな「構造的な賃上げ」について、ポイントをみておきましょう。
「構造的な賃上げ」の3つの課題
【1.賃上げ 2.労働移動の円滑化 3.人への投資】
● 3つの課題の一体的改革を進め、次のような方向性を示す
1. 官民が連携して、現下の物価上昇に見合う賃上げの実現に取り組む
民間給与の伸びを踏まえた改善等を図るとともに、看護、介護、保育をはじめ、現場で働く方々の処遇改善や業務の効率化、負担軽減を進める
2. リスキリング(学び直し)への支援策の整備や、年功制の職能給から職務給への移行
企業間、産業間での労働移動円滑化に向けた指針を、来年6月までに取りまとめる
個人のリスキリングに対する公的支援は、「5年間で1兆円」のパッケージに拡充
あわせて、同一労働同一賃金について、その遵守を一層徹底する
3. フリーランス法の整備
個人が、フリーランスとして安定的に働ける環境を作るべく、法整備にも取り組む
4. 公正取引委員会等の執行体制を強化
中小企業における賃上げに向け、生産性向上とともに、価格転嫁を強力に進める
* 「労働移動円滑化に向けた指針(来年6月までに取りまとめ)」や「人への投資策(5年間で1兆円のパッケージに拡充)」が注目を集めています