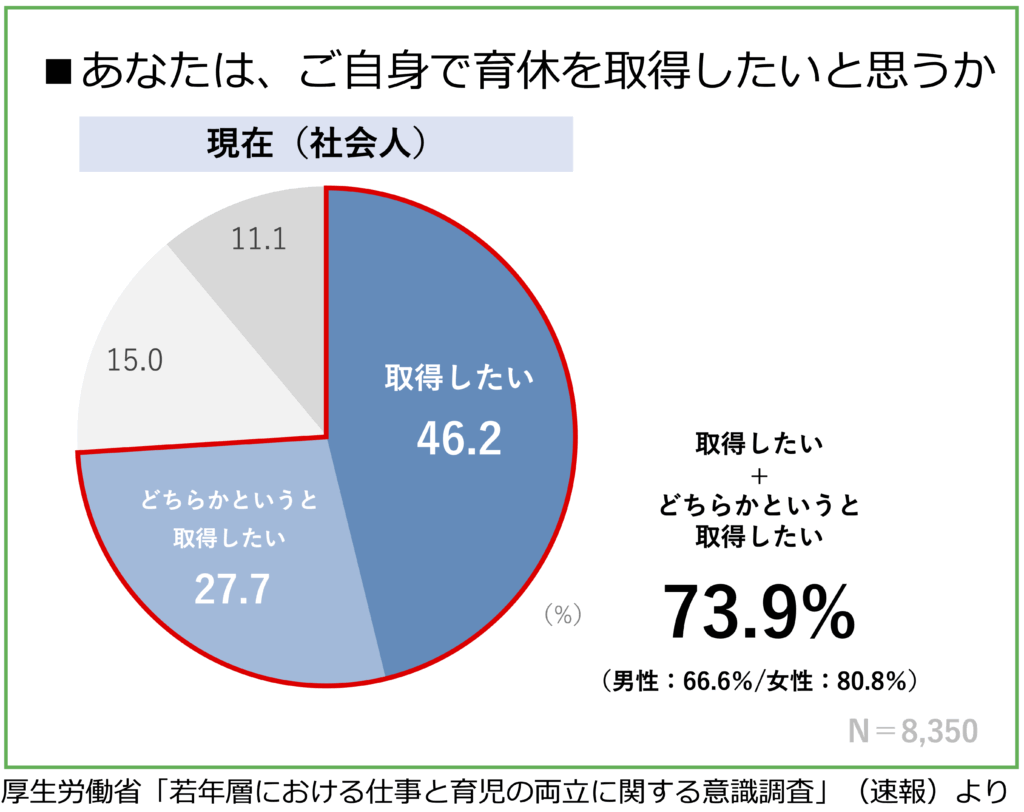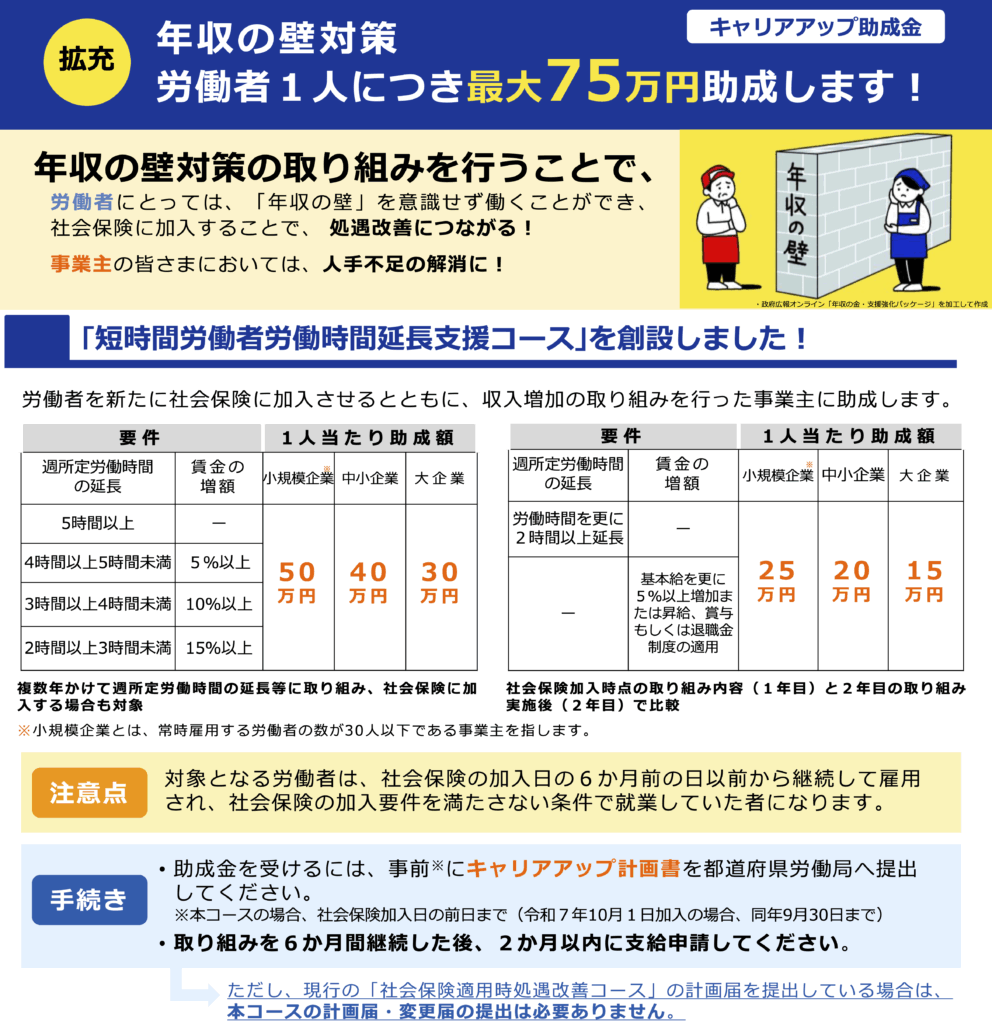厚生労働省は、令和6年度に長時間労働が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した監督指導の結果を取りまとめ、監督指導事例とともに公表しました。監督指導事例から自社が違反をしていないのか定期的に確認をしておきましょう。
主な監督指導例
1.36協定で定めた上限を超えて時間外労働を行わせた(是正勧告)
2.労基法で定められた上限を超えて時間外・休日労働を行わせた(是正勧告)
*時間外・休日労働時間1か月あたり80時間以内とする具体的方策の実施確認を行う
3.勤怠管理システム上の残業申請の時間と、タイムカード打刻記録との間に1日あたり3時間程度の乖離があり理由が不明(監督指導)
*労働時間を訂正に把握するための具体的検討・実施をすること
*過去に遡って労働者に事実関係の聞き取り等に実態調査委を行い、未払い賃金がある場合には支払うこと